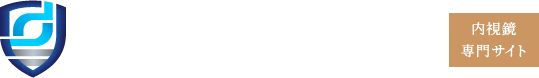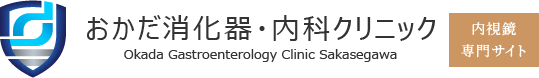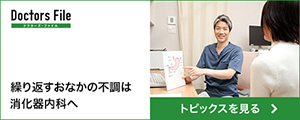宝塚市・逆瀬川にある「おかだ消化器・内科クリニック」は、地域の皆様の健康と笑顔を守るため、日々の診療に取り組んでおります。内科・消化器内科を専門とする医師として、患者様お一人おひとりの症状に合わせた丁寧な診療を心がけ、予防から治療まで幅広くサポートしております。
このブログでは、当院での診療内容や、皆様の健康管理に役立つ医療情報を、わかりやすくお届けしてまいります。
今回は、「過敏性腸症候群」と「潰瘍性大腸炎」の違いと、適切な対処法についてお話しいたします。
突然のお腹の不調、その原因は?
仕事中や外出先で突然お腹が痛くなり、トイレに駆け込んだことはありませんか?
どなたでも、特に悪いものを食べていないのに下痢になったり、腹痛に悩まされたりしたという経験があることでしょう。
こうした予期せぬお腹の不調の背景には、「過敏性腸症候群」や「潰瘍性大腸炎」といった病気が隠れている可能性があります。どちらも原因が明確でない上に、腹痛や下痢といった症状が共通しているため、見分けが難しい病気であると言えます。
2つの病気の共通点
過敏性腸症候群と潰瘍性大腸炎には、次のようないくつかの共通点があります。
- 腹痛や下痢などの症状がある
- ストレスによって症状が悪化することがある
- 症状を繰り返し、日常生活に支障をきたす
- 本人以外には理解されにくいつらさがある
2つの病気の決定的な違いとは?
似た症状を持つこの2つの病気ですが、見分けるうえで重要な違いがあります。
まず、過敏性腸症候群では、腸に器質的な異常(炎症や潰瘍など)は見られません。下痢や便秘を繰り返しますが、血便は通常見られないのが特徴です。また、排便すると腹痛が軽減することも過敏性腸症候群の特徴と言えるでしょう。
一方、潰瘍性大腸炎では、大腸の粘膜に実際に炎症が起き、下痢だけでなく血便や粘液便などの症状が見られます。これは、大腸の粘膜に潰瘍やただれ(びらん)が生じ、そこから出血するためです。
さらに、異なる点として挙げられるのは、病気の重症度です。
過敏性腸症候群は生命を脅かす病気ではなく、通院での治療が可能です。しかし、潰瘍性大腸炎は国の「指定難病」に定められており、まれに重症化すると命に関わる危険性があります。
それぞれの治療法の違い
治療アプローチも両者で異なります。
過敏性腸症候群の治療
過敏性腸症候群の治療では、生活習慣の見直しやストレス管理が中心となります。患者様の状態に合わせた生活習慣の改善のほか、必要に応じて症状を和らげる薬を使用します。
潰瘍性大腸炎の治療
潰瘍性大腸炎の治療では、大腸の炎症を抑えることが最優先です。主に薬物療法で炎症をコントロールします。
多くの場合、適切な治療により症状が改善しますが、ストレスなどがきっかけで再発することもあるため、継続的な管理が必要です。
正確な診断と治療のために

過敏性腸症候群と潰瘍性大腸炎は症状が似ているため、正確な診断が極めて重要となります。自己判断で対症療法を続けることで、かえって症状を悪化させてしまうことも考えられるからです。
お腹の不調が何であるかを正確に診断するためには、大腸カメラ検査(大腸内視鏡検査)が欠かせません。当院では日本消化器内視鏡学会専門医の資格を持つ女性医師が、できるだけ苦痛の少ない内視鏡検査を心がけています。
また、検査の説明から実施、結果の説明まで、すべて女性スタッフで対応することも可能ですので、女性の方も安心して検査を受けていただけます。
腹痛や下痢などの症状が続く場合は、お早めに専門医に相談することが大切です。お腹の不調でお悩みの方は、お気軽に当院へご相談ください。