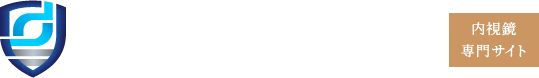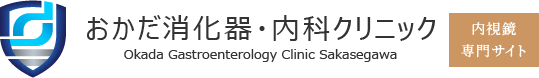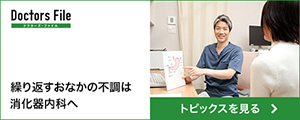宝塚市・逆瀬川にある「おかだ消化器・内科クリニック」は、地域の皆様の健康と笑顔を守るため、日々の診療に取り組んでおります。内科・消化器内科を専門とする医師として、患者様お一人おひとりの症状に合わせた丁寧な診療を心がけ、予防から治療まで幅広くサポートしております。
このブログでは、当院での診療内容や、皆様の健康管理に役立つ医療情報を、わかりやすくお届けしてまいります。
今回は、炎症性腸疾患とストレスの関係についてお話しいたします。
炎症性腸疾患(IBD)とは
炎症性腸疾患(IBD)は、国の指定難病に認定されている慢性的な消化器疾患で、大きく潰瘍性大腸炎とクローン病の2つに分類されます。これらの疾患は腸管に慢性的な炎症を引き起こし、腹痛や下痢、血便などの症状を繰り返します。
特に10代後半から30代の若年層に多く見られ、症状の程度には個人差がありますが、日常生活に大きな影響を与えることもある疾患です。
ストレスと炎症性腸疾患の関係
「ストレスが原因なのでは?」というご質問がありますが、炎症性腸疾患は遺伝的要因、腸内環境、食生活など複数の要素が関わる疾患であり、ストレスが直接的に病気を引き起こすという証拠は示されていません。
ただし、ストレスは腸と脳の相互作用(脳腸相関)を通じて、消化管の機能に影響を与えることがわかっています。
例えば、ストレスを感じると…
- 腸の運動が変化する
- 腸の血流が減少する
- 腸の粘膜のバリア機能が低下する
- 免疫系の反応が変化する
といった変化が起こり、すでに炎症性腸疾患を持つ方の症状を悪化させる可能性があります。また、ストレスによる生活習慣の乱れ(睡眠不足、食事の不規則化など)も症状に影響することがあります。
つまり、ストレスは炎症性腸疾患の直接の原因というよりも、症状を悪化させる「引き金」になり得ると考えられています。
炎症性腸疾患の検査と診断
炎症性腸疾患が疑われる場合、以下のような検査を行います。
内視鏡検査(大腸カメラ)

炎症の程度や範囲を直接観察し、必要に応じて組織を採取して詳しく調べます。診断の確定や経過観察を行うために欠かせない検査です。
当院では、日本消化器内視鏡学会専門医の資格を持つ女性医師が、できるだけ苦痛の少ない内視鏡検査を心がけています。検査の詳細な説明から実施、結果説明まで、すべて女性スタッフでの対応も可能ですので、女性の方も安心して検査を受けていただけます。
その他の検査
■血液検査
・炎症の程度や栄養状態を確認
■便検査
・感染性腸炎との区別や炎症マーカーの確認
■画像検査
・腸管の状態を確認
ストレス管理と生活習慣の改善
現代社会でストレスを完全に避けることは難しいですが、炎症性腸疾患の改善のために、以下のようなストレス管理を心がけることが大切です。
- 適度な休息と十分な睡眠
- 規則正しい生活リズムの維持
- 適度な運動
- 趣味や好きな活動を楽しむ時間を持つ
- 必要に応じてリラクゼーション法を取り入れる
また、炎症性腸疾患の方は、食事管理も重要なポイントとなります。1日3食、規則正しい時間に食事をとり、消化に負担をかけない食品選びを心がけましょう。
症状が気になる方は、お早めにご相談ください

炎症性腸疾患は、現時点では完治させることは難しいものの、適切な治療と生活管理によって症状をコントロールすれば、通常の生活を送ることは十分可能な病気です。
気になる症状がある場合は、お早めに専門医に相談することをお勧めします。
当院では、患者様お一人おひとりの状態に合わせた丁寧な診療を心がけています。炎症性腸疾患に関するご不安やご質問がございましたら、お気軽にご相談ください。